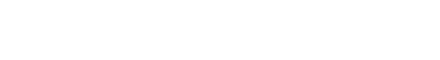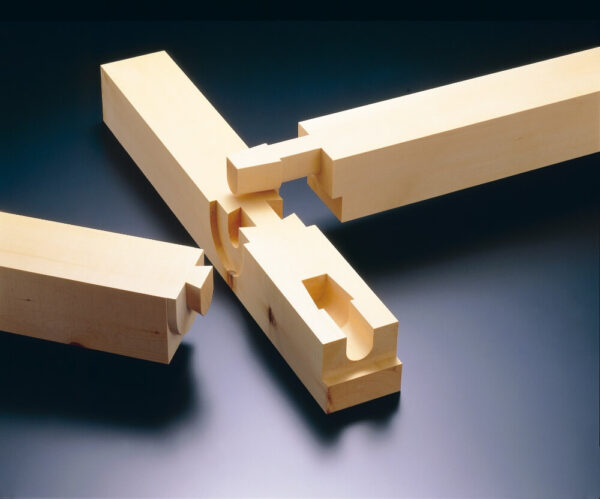コンクリートを流しこむまでの流れです。
前回に続き2回目のコンクリート打ちです。


2回目のコンクリートを流す前にも
重要なチェックポイントがあります。
アンカーボルトチェックです。
アンカーボルトは鉄の棒で
通常直径12ミリと16ミリのものを使用します。
後で登場する専用の金物とセットで
〝基礎と建物の木造部分をつなげる〟
というとても重要な役割を果たします。
アンカーボルトはコンクリートに埋め込む長さが種類によって
きっちり決まっています。
↓これです。
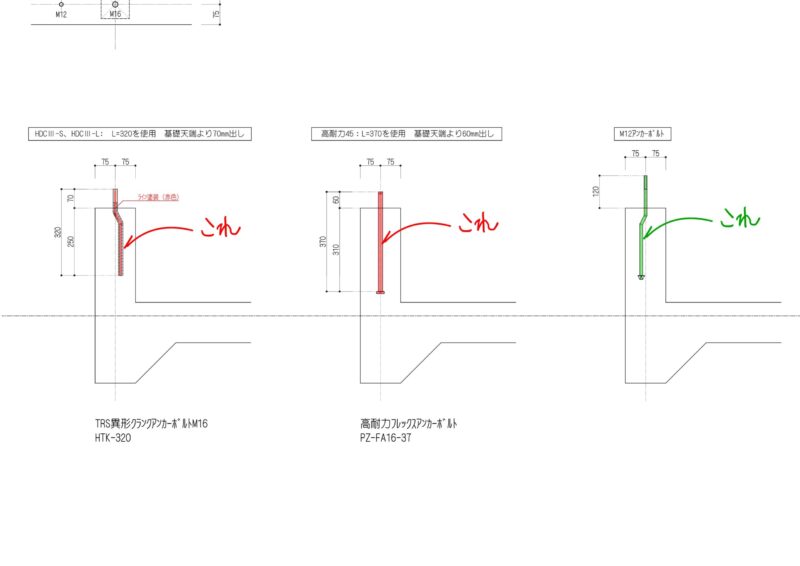
コンクリートを流す前に頭が少し出るように仕込んで
コンクリートの中に埋めてしまいます。
↓コンクリート打設前の仕込み状況


↓仕上がり(他現場写真)

アンカーボルトが無いと
いくら強固な基礎の上に強靭な建物を建てても
大地震の際、建物が基礎から離れてしまい
倒壊してしまいます。
なのでしっかりアンカ-ボルトを設置して
基礎と建物を緊結する必要があります。
コンクリートを打った後では入れ忘れに気づいたとしても
どうしようもありません。
構造計算をすると
地震や台風の際、
建物のどの辺がどの程度浮き上がりやすいかが
分かります。
なのでどこにどういった強度のアンカーボルトが必要か
分かるわけです。
例えば建物左下(3-い通り)は
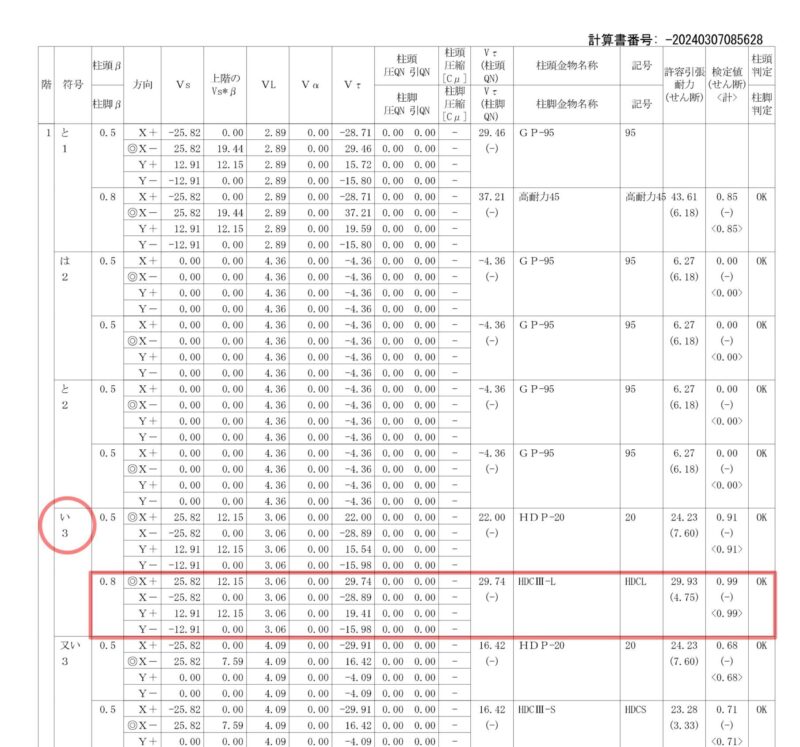
という計算結果で
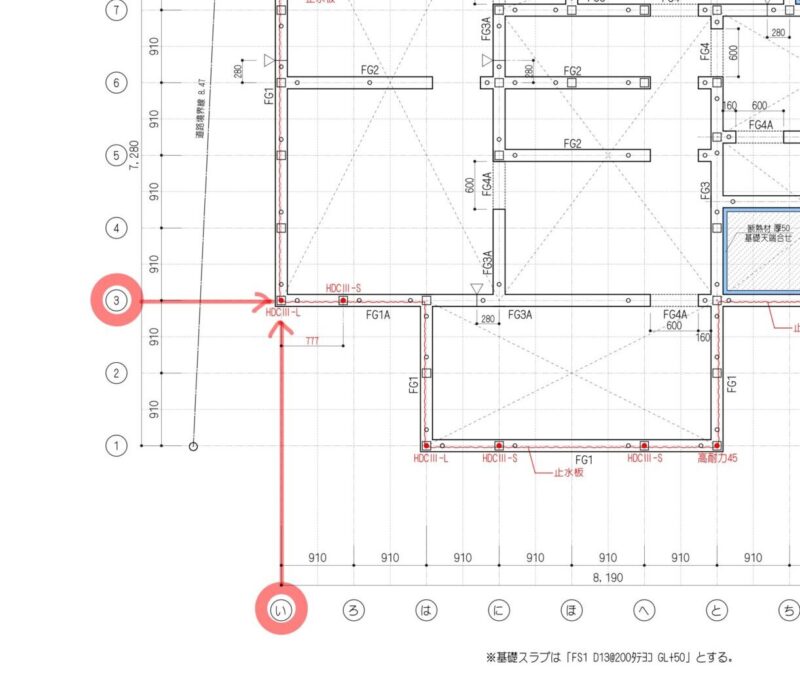
必要なアンカーボルトが決まります。
※構造計算では今回の柱脚(つまり足元)の計算だけではなくて
柱上部に必要な金物耐力も割り出します。
1階2階、すべての柱位置で計算をしてすべての箇所に
計算結果に合った金物が設置されるわけです。
耐震等級が1でいいよとする場合と
耐震等級3を確保する場合とでは
当然計算結果が変わり必要な金物も変わってきます。
どんなに強固は金物を使っても計算結果がNGとなる場合は
間取り変更が必要になるわけですね。
今回の基礎では16ミリのアンカーボルトが
強度違いの2種類で計9本、
―特にこの16ミリのアンカーボルトは重要―
12ミリは数えるのがめんどくさいほど入っています。
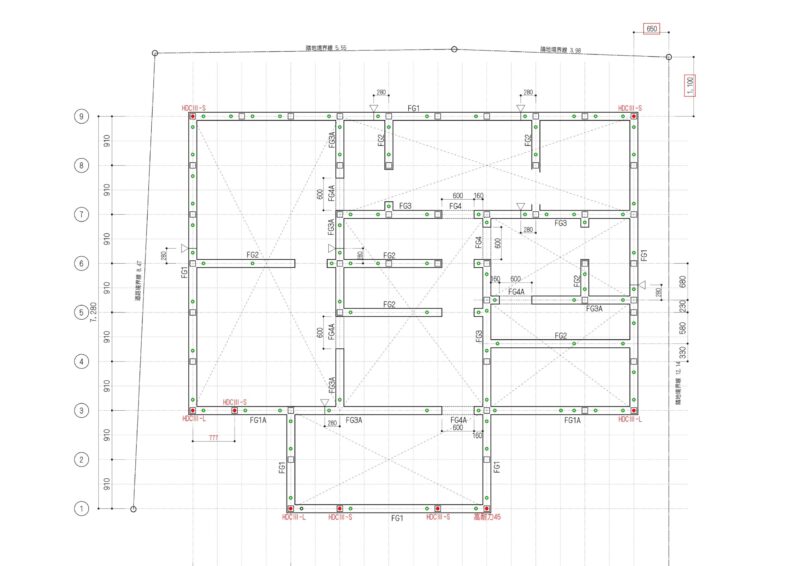
↑
赤色が16ミリのアンカーボルト
緑色が12ミリのもの。
今回の新規格は今までと違う建物の構造様式にしています。
木造は木造なのですが、〝金物工法〟の木造となります。
今までは〝在来工法〟でした。
違いはまた別ブログで紹介します。
在来軸組み工法から金物工法に変わったことで
16ミリのアンカーボルトも今までとちょっと違います。
我が家と何か違うぞと気づかれたOB様、
強度や内容は変わりませんのでご安心ください。
全箇所きっちり確認して
ようやくコンクリートを流し込み、
固まれば基礎完成です。
(余談ですが、私が戸建リフォームに積極的ではない理由は
この辺が関係しています。
さっきも書きましたがアンカーボルトは後施工ができません。
もし出来たとしても建物が倒れるのを支えるだけの強固な基礎
でなければ意味がありません。
建物は強くできますが、
それに見合う様に基礎の強度を上げ、
建物と基礎をつなげるのは
とても難しいと思うのです。)